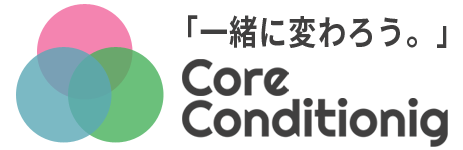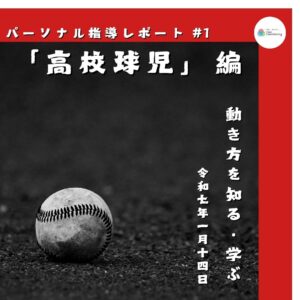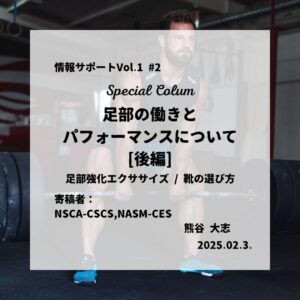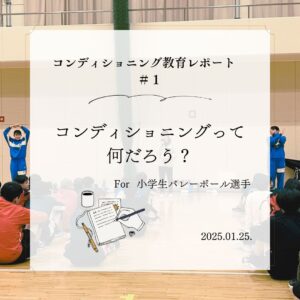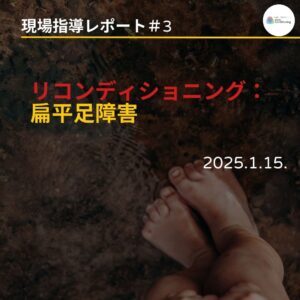高校男子バレーボール選手の対応をしました
このチームには”学生トレーナー”がいます。高校生ながら、ストレッチングやテーピングなど、自分で調べながら日頃は対応しているようです。こうしてトレーナーの役割に興味を持ってくれるのは嬉しいことなので、時々、現場に行って、彼女の困り事を聞きながら選手の対応をしています。
今日もたくさん私のところに選手を連れてきました。それ以外にも選手の方から動き方など相談に来てくれました。たまにフラッと顔を出す程度なのに、嬉しいことですね。。
今日対応した外傷・障害で多かったのは腰痛でした。原因として太ももの後ろの筋肉(ハムストリングス)と股関節の前あたりにある筋肉(腸腰筋)の柔軟性が低下し、骨盤が前に傾くことで、腰が反った状態で筋緊張が続いている、というのが多かったです。
すでに医療機関で腰椎椎間板ヘルニアの診断を受け、安静が必要な選手も中にはいました。椎間板という背骨と背骨の間にあるクッションが潰れて、神経を圧迫し脚に痺れなどの神経症状が出てしまうものです。コルセットを装着していたので、今日は痛みがない範囲で腹圧をかけるような”臍のぞきの腹筋”を指導しましたが、ストレッチ痛もあったので、今は動きのあるものは控えて、医師に言われる通り、安静が先決ということやヘルニアの発生要因、予防について説明しました。
バレーボールは、ボールをヒットするたびに、少なからず腹筋や背筋の運動はしているようなものですが、プレーによる腰痛の予防で大事なのは、表面の筋(アウターマッスル)の強化ではなく背骨、そして骨盤を安定させる腹部(腹横筋、腹斜筋など)や背部(多裂筋)などのインナーマッスルが働いてくれるような鍛え方、そして腸腰筋のように脚と体幹を繋ぐ筋や、ジャンプするときに床にしっかりと踏み込むためにお尻周りの筋肉が十分に機能するために、日頃から筋肉の柔軟性(柔らかさ)を確保することもポイントとなります。しかしながら、トレーニング動作の習得もなかなか時間がかかるため「こちら(教える側)とあなた(本人)、お互いの努力が必要」だと腹を括って繰り返し指導するしかないのが現実です。
「肩周りの柔軟性をつけるにはどんなストレッチをしたらいいですか?」とスパイクするときにもっと大きく腕を動かしたい・・・と具体的に相談してくる選手もいました。こういう要求の場合、できるだけスパイク動作をイメージしやすい形で指導します。動かせていないであろう筋肉を、意識して動かすためにはどういう”感覚”なのか、を教えます。いずれにせよ、肩というより肩甲骨の動きを出さなければならず、そのためには胸周りを動かす必要があります。胸を動かそうと思えば、そこを支える腰部やお尻周りが安定していないと、動かせません。結局は「あなたがすでに持ち合わせている体幹部をしっかりと使おうね」という表現に尽きます。
”一般人あるいはアスリートいずれに関わらず、四肢の筋量や筋力における性差は、下肢より上肢において表れる”(金久博昭 著.2016.)とある。特にこの時期の男の子は男性ホルモンの分泌が活発になる時期なので、ウエイトトレーニングなどで負荷をかけてしっかり筋肉に刺激を入れたいところですが、トレーニング環境(安全性が保障される器具やスペース、専門家の指導を受けられる、など)が整っていることがリスク回避の条件だと思うので、今はこの環境でできることをしっかりとやることが大事です。まだまだ今の環境でもできることはありそうなので、伸び代を伸ばすだけ伸ばす努力を積んで、頑張って欲しいと思いました。