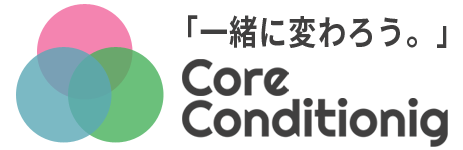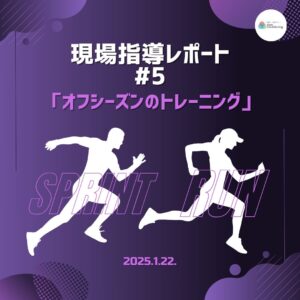トレーニング指導をする上で大事なことはトレーニングの計画を立てることです。その流れはフィジカル測定、年間の期分けに沿ったトレーニングプログラム作成、実施、モニタリングそして測定によるチェックです。
”期分け(ピリオダイゼーション)”は、年間の試合日程に応じてトレーニング期を分けることです。トレーニング期は一般的にはオフシーズン(準備期)、プレシーズン(専門的準備期)、インシーズン(試合期)。大学生大まかな年間の大会スケジュールは春季(4月〜6月)と秋季(9月〜11月)、そして12月に全日本インカレというふうに、大きく年間を2期に分けた構成となっています。
現在、大学生はオフシーズン。期間として12月〜2月の約3ヶ月間は一般的な準備期として、基礎体力の向上に時間を捻出する練習スケジュールとなっています。
●超回復理論の考え方(汎適応症候群)
ピリオダイゼーションの基本となる考え方は汎適応症候群として提唱される人間のストレス適応のメカニズムです。体にトレーニング負荷というストレスがかかることで、急性的な疲労が起こりますが、適切な休養や栄養でリカバリーをしつつ再びストレスをかけていくことで、元の状態よりも体力レベルが上がる効果を狙ったものですが、このストレスも徐々に高く、そして継続してこのサイクルを繰り返すことで成長が図れるものなので、長期的なトレーニング計画はストレングスの強化には必要不可欠な資料となります
●トレーニング計画
大学生の場合はシーズンがはっきりしているのでプログラムは比較的立てやすいのです。ただ、高校生の場合は年間通して大会が数多くあり、なかなか体力トレーニングだけに焦点を当てて練習時間を費やすことは難しいです。私は「ブロック戦略」という考え方を採用しています。この戦略は小さな期分けを繰り返して、メインとなる大会に向けてピーキングを行う方法です。このようにトレーニング対象や競技、目的によっても変化させる場合もあります。
オフシーズンは普段、技術練習に費やされる時間をトレーニングに回していただけるので、とにかく単純な動きで「量」をこなすことがメインとなります。ウエイトトレーニングは回数とセット数を増やす、中距離を繰り返し走るなど、競技特性からあえて離した動作を取り入れます。走る、跳ぶ、投げるなどの運動の基本動作をこのシーズンではあえて取り入れます。このシーズンで培ったフィットネスの幅は、この後1年間、パフォーマンスを支える体力の下地となります。そして大学4年間で積み上げていくことによって最終学年で最も安定した体力を獲得し、技術習得に反映してくることを経験しています。
今日はランニングトレーニングを設定した日でした。50m×4本×4セットを1:3のインターバルで実施しました。日によっては300mのインターバル走も設定し、それぞれ目的を変えて実施しています。主に観たのは走り方。オフシーズンの前半に走り方のドリルを導入しているのでそれぞれ腕振りや脚の引き上げは意識していたと思いますが、動きのエラー動作の根本原因はバレーボールのスキルにもつながってくるので重要な個人の情報です。この後、エラー動作をしていた選手には、原因と改善した方がいい理由などを別途ストレッチングや体幹トレーニングで動きの変化を指導しました。トレーニングプログラムをこなすことも大事なのですが、このような取り組み(モニタリング)がトレーナーとしては一番やらなければいけない仕事だと感じています