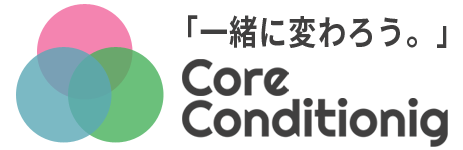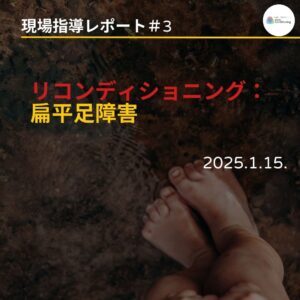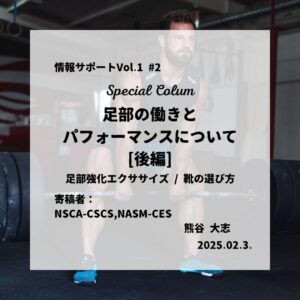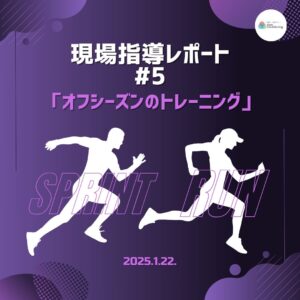今回は私がサポートしている大学生チームのトレーニング指導の様子です。
大学生アスリートは競技歴が長くそこそこ競技レベルが高い選手が集まっている集団です。これまで積んできた経験値や体得したプレーの感覚など体に刻み込まれた選手の能力を目の当たりにする場面が多いので、『トレーナー冥利に尽きる』現場です。
昨日は2月末までのトレーニングプランと新たなドリル(体幹メニュー)指導とウエイトトレーニングのフォームチェックをしました。
●体幹トレーニング
「スタビリティドリル」と「ストレングスドリル」に分けてます。「スタビリティドリル」は体幹と骨盤を安定させた状態から脚や腕を動かしたり、体幹を捻ったり。代表的なエクササイズはプランクですがサイドプランクとフロントプランクの切り替え動作を入れてみました。「ストレングスドリル」はMB(メディシンボール)を使ったり、四股踏みしたり主に立位姿勢の中で刺激を入れたり、ボールを投げたりキャッチしたり、パフォーマンスに近い形で組んでいます。
●ウエイトトレーニング
最大筋力は様々なスポーツ動作においてパワー発揮能力を高めるための基盤となる(Gadeken,1999).またより最大筋力の高いアスリートほど大きなパワーを発揮できることが報告(Barker,2001;stone et al.,2002)されており、パワー発揮能力を高めるためには最大筋力を高める必要がある(岡野ほか,2017)、というようにパワー発揮が求められるバレーボールにおいて最大筋力の向上は大事だと考えます。
筋力向上を目的に週2回、補助トレーニング週1回のプログラムです。ウエイトトレーニングも重い重量になるほどリフトの技術が必要です。チームに求める「課題」は提示しつつも、一人一人の取り組み方は違うこと、学年によっても(トレーニング歴の違いから)目的は変わることを伝え、4年間かけて技術習得しつつ重さが持ち上げられるようチャレンジするよう指導しています。スクワット1つ取ってみてもちょっとした重心の位置や感覚の違いで使う筋肉が違います。昨日も微妙なポイントでフォームが安定し「軽い!」と言う選手もいるし、まだまだうまくコツを掴めない選手もいます。
選手はとにかく「うまくなりたい」。でもどちらかというと女の子は、あまり余計なことをするのは好きではないので、体力トレーニングも積極的ではありません。体幹トレーニングは基本的な体幹の使い方をしっかりと認識させ、さらにバレーボールのプレーでどう繋がるのか伝え、納得すると取り組んでくれます。最終的には量をこなさなければならないので、トレーナーも「指導力」は必須ですね・・・個々に合わせて”伝える技術”は求められます。
身体の使い方は確かに大事ですが、実際にやるのは選手です。選手を心を動かし継続させる環境づくりは単に体力の向上だけでなく「だからパフォーマンスが向上した」という理由づけにならなければなりません。
そのためには私自身が身体を使って体得し、感覚を噛み砕いて自分の言葉を生み出していくことが一番。選手以上にこちらの努力と学び、柔軟な対応力とコミュニケーションは現場で繰り返し経験積んでいくしかないですね。