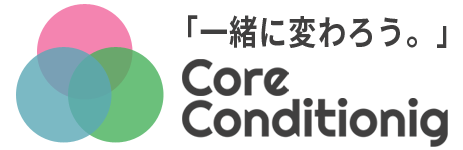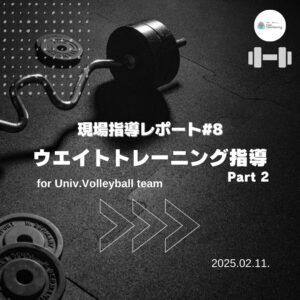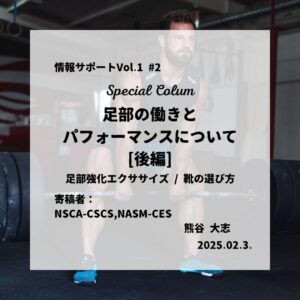選手が練習している姿をよく観察していると、うまく動けていない選手、うまくこなせている選手、それぞれの姿があります。今日の練習では「体幹が不安定」な選手が目につきました。
実際に体幹トレーニングしている選手は体幹筋は大事だと認識しつつも、その効果や影響をイマイチ実感できないことがほとんどです。「キツイか、キツくないか」という主観的な運動強度がトレーニング効果だと勘違いしている人も多いように感じます。実は体幹筋が十分機能すると、トレーニングは「楽に」「沢山こなす」ことができるのですが個々に応じたアプローチが必要です
今回は体幹トレーニングを行う際のポイントとパフォーマンスとの関連を選手に説明しました。パフォーマンスを支えるフィジカルは総合的なコーディネーションです。トレーニング指導の難しさや奥深さが伝わればと思います。
<内容>
●体幹トレーニングを行う意味と目的
●プログラムを与える危うさ
●パフォーマンスへ活かすために
●体幹トレーニングを行う意味と目的
少し、基本的なことになりますが、体幹トレーニングの一番の目的は姿勢のコントロールです。
体幹部は深層部(腹横筋、多裂筋など)、中間層(内腹斜筋、外腹斜筋、中臀筋など)、浅層部(腹直筋、脊柱起立筋、広背筋など)に分けて考えられており、そのうち姿勢は深層部の筋群が重要な役割を担っています。
背骨の前面(お腹)には内臓があります。その内蔵を所定の場所に収めている薄い膜状の深層筋、周囲を取り囲むように中間層、さらに表面に重なるように浅層の筋群がコルセット様となり、内臓を守り、背骨を安定させています。
また脚の筋肉は骨盤に多く付着するため、骨盤と脚の骨で構成される股関節は十分に動きを確保しつつ、骨盤が過剰に前や後に傾かないよう、安定性(スタビリティ)を保つためにいわゆる「体感トレーニング」の代表的なドリル、プランクが実施されています。
地球は、重力という外力が常にかかっています。重力に抗し、アライメント(骨格)を維持する筋力は最低限必要で、自身を目的とする場所へ移動したり、跳んだりスポーツ動作を起こすためには関節を動かす原動力となる筋肉が必要となります。その一番コア(中心=背骨を支え骨盤を安定させる)となる部分が弱くしかるべき機能がなされなければ、筋肉は柔軟性を欠き関節は動きを損ないます。柔軟性を失った筋は硬く、鉛のような重さを与え、”痛み””パフォーマンス低下”などの不具合を生じます。
スポーツ動作はさまざまな姿勢でプレーすることが求められます。姿勢の良し悪しとは単に”立っている姿が美しい”ことを指しているわけではありません。ただ、不良姿勢のまま激しいスポーツ活動を行うとケガが発生したり、パフォーマンスが効率よく実行できません。
コンディショニングの目的は「ケガをしにくい体を作ること」と「パフォーマンスの向上」です。つまり体幹部の不安定さは根本的なコンディショニングの目的から外れてしまう要因になり得る。だからとても重要だと捉えています。
●プログラムを与える危うさ
トレーニングプログラムを作成して実施してもらうのが私の役割です。確かに学生たちはトレーニングをこなしていますが、体幹の不安定性が見え、パフォーマンスが安定しないのはなぜでしょうか?
1番目の問題点は、紛れもなく私の指導力不足です。目的を十分理解させてトレーニングを行わせられていないことが原因でしょう。申し訳ないですが、これは私が精進するしかありません。
2番目は選手自身の理解度が低くトレーニング量をこなせていないこと。ある程度量をこなさなければ使い方や理解が深まるまでには至らないのですが、なんというか「できてない」のです。
指導していて”難しさ”を感じるのは「プログラムをこなすこと」が目的となってしまうこと。だから「できてない」し選手は「やっている」という。理解と意識を得られるまでは時間がかかるし、やらないよりはいいと考えることも大事だと思うようにしていますが・・・やっぱり自分の指導力の無さは否めず、悔しいです。
●パフォーマンスへ活かすために
例えば、レシーブの時、サーブやスパイクでボールを叩く時、ブロックする時などボールに力を加える、あるいは外力に抗する場合・・・ジャンプする、ステップを踏む、ストップするなど自分の動作を起こす瞬間的な場面でも体幹筋が機能すれば、全く違う感覚で動く事が出来る。MB(メディシンボール)を使ってキャッチする、投げる、叩きつけるなど、負荷をかけて動作を行わせてみることも取り入れていますが、なかなか結果(パフォーマンス向上)が思うように導けなくてずっと考え続けています。
”ジャンプ動作時に腹横筋は外腹斜筋や腹直筋よりも有意に早く活動し,蹴り出し期(push-off phase)にて大きな地面反力を受ける準備段階として働くことを報告している*” という報告があります。「有意に早く」というのはフィードフォワード制御*のことを指します。*フィードフォワード制御:環境や外的な刺激に応じて脳の指令が出て動く(随意運動)前に、適切な身体コントロールを無意識下で司どる機能のこと
無意識下で起こることだから、結局は選手も(指導者も)変化を自分で感じ、掴まなければわからないんだと思います
残念ながら動画や写真、言葉では伝えること、魔法のようなドリルはありませんが、パフォーマンス中の体幹筋の機能を最大限に発揮させるきっかけや、発揮できた先に起こるパフォーマンスの変化を長年追求してきた結果、ようやく私なりの答えと選手への伝達が合致した、そんな瞬間があることは確かに感じています。
●まとめ
体幹筋の主な役割は姿勢コントロールです。何層にも重なる体幹筋のうち、深層部の筋(腹横筋)は重要な働きを担います。骨盤の傾きによって背骨の動きは変化し頭部の位置に影響します。目(視覚)で情報を得て咄嗟の判断で行動をしなければならないアスリートにとって、体幹筋が弱いことで姿勢が崩れ、視覚の情報キャッチが遅れてしまっていること、環境と自身の空間認知能力にまで影響しているかもしれないことは技術習得にも支障をきたすことになると感じます。
選手に伝えたいのは、身体に起こっている痛みというサインを無視せず「なぜだろうか」という疑問を持つこと、与えられたトレーニングの目的を知る権利があり、理解するまで相談することです。
そして自分の体を自分で守るための知識と行動選択が必ずあることを今後も伝えていきたい(必要だと思ってもらえるように)と思います。
*引用文献:日本アスレティックトレーニング学会誌 第 5 巻 第 1 号 3-11(2019),体幹筋機能のエビデンスとアスレティックトレーニング,大久保 雄